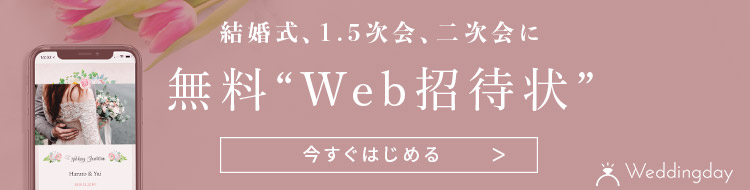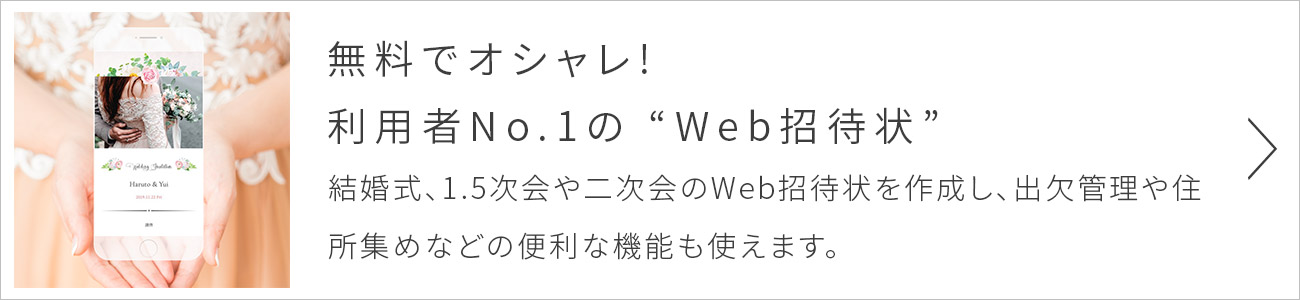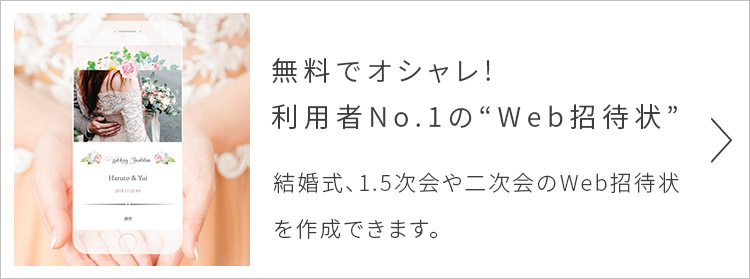結婚式には誰を呼ぶ?招待客の決め方や注意点を解説

結婚式の準備を進めるなかで、ゲストとして誰を呼ぶか悩むカップルは多いもの。親族・上司・同僚・友達など、どこからどこまで呼ぶかは、事情によって異なるので線引きが難しいですよね。
そこで今回は、結婚式に誰をどこまで呼ぶか、スムーズに決める方法や流れをご紹介。また、招待客を決める際に注意しておきたいポイントも解説します。これから結婚式を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
結婚式には誰を何人呼ぶ?関係性別に解説

結婚式や披露宴などに、招待客として誰を何人呼ぶかは重要なポイント。招待客は結婚式の雰囲気や予算にもかかわるためです。
式場のキャパシティや相手との関係性、結婚式・披露宴の雰囲気をどうしたいかを考え、慎重に選ばなければなりません。
たとえば、親族中心の結婚式ならアットホームな雰囲気、職場の上司など目上の相手が大勢いるならおごそかな雰囲気、友達が多いならカジュアルな雰囲気など、招待客層によって結婚式や披露宴の雰囲気が変わる場合もあります。
・パートナーの招待客とのバランス
・親族の意向
・どんな規模・雰囲気の式にしたいか
などを踏まえたうえで、誰を呼ぶかを決めることが必要。式場の決定は招待客の客層や人数が大体決まった後がおすすめです。具体的に、関係性別で誰をどこまで呼ぶかの目安をご紹介します。
親族
結婚式に親族のなかでも誰を招待するかは、特に決まりはありません。一般的には両親、兄弟姉妹やその配偶者と子供(甥や姪)、祖父母、伯父伯母までが目安とされています。
しかし、日頃から交流があるか、関係性が近いか、地域の風習があるかなどによって呼ぶべきかは変わるので、両親と相談して決めるのがおすすめです。
また、結婚式に呼ばないと決めた親族への配慮も忘れないようにしましょう。納得できるような理由を説明するほか、事前の結婚報告はしっかり行うことが大切です。
友達
結婚式で最も悩むのが、友達をどこまで呼ぶべきかという方も多いのではないでしょうか。「友達」とひとくちに言っても付き合いが浅い人から深い人まで、関係性はさまざま。場合によっては、友達関係を壊してしまうことも考えられるため、慎重に選ぶことが大切です。
まず、一番大切にしたいのが、今後もその人と関係を続けていきたいかどうかで招待するゲストを決めること。そのなかで、親しい友達や、過去に結婚式に招待してもらった友達を呼ぶのはマナーです。
また、同じ友達のグループ内で、招待する人と招待しない人を出さず、全員を招待することも大切。万が一理由があって、グループ内でも招待しないゲストがいる場合、グループのメンバーにも事情を話しておき、結婚式の話題を避けるのが無難です。
職場・仕事関係
職場・仕事関係の人は、必ずしも結婚式に招待する必要はありません。先に結婚式を挙げた上司や同僚などに、誰を呼んだか聞くのがおすすめです。また、会場のキャパシティはもちろん、関係性や職場の慣習に合わせて選ぶことが大切です。一概に親しさだけを重視すればよいわけではなく、肩書きも重視して決めましょう。
職場・仕事関係の人を招待することになったら、直属の上司は必ず呼びます。乾杯の音頭や祝辞を頼む場合は、余裕を持って依頼しておきましょう。
また、部署が変わったなどの事情で、遠方に住んでいる上司を招待する場合、特に乾杯の音頭をとってもらった場合は、お礼の言葉とともに、最低でも1万円を「お車代」として包むのがマナーです。
職場・仕事関係の相手は今後もお付き合いを続けていく大切な方々。もし結婚式に呼ばない場合も、結婚報告を丁寧にしたり、2次会に呼んだりとフォローすることが大切です。
結婚式に誰を呼ぶかを決める方法
結婚式の規模や招待人数で決める
親族や親しい友達のみで式を挙げる場合

親族のみの結婚式は、文字通り親兄弟や親戚のみを招いて式を行うスタイル。どの規模の式でも、親族は必ず席が必要な招待客です。
ただし、親族とひとくちにいっても、関係性によってどこまで呼ぶかの線引きは難しいもの。まずは両家の間で誰を呼ぶか決める必要があります。両家の両親に相談したうえで、呼ぶ親族を決めましょう。
また、親族のみでの式の場合も、特に関係の深い友達を招待する場合もあります。あまり多くなりすぎないように、親族の人数を考慮してから誰を何人呼ぶかを決め、人数を決定しましょう。
49人以下の少人数で行う場合

招待人数が49人以下の結婚式は「少人数ウエディング」と呼ばれます。親族を中心に、会社の上司や親しい友人、非常にお世話になっている方など、心から来てほしい方を決めましょう。
友達同士で「○○ちゃんは呼ばれているのに、私は呼ばれていない」などとならないよう、周りの人間関係にも配慮が必要です。
50人以上の大人数で行う場合

招待客が50人以上の中規模・大規模で結婚式を行う場合、親族から順番に、まずは「絶対に呼びたい人」を決定しましょう。その後、誰を呼ぶかを決めていきます。
大人数を収容できる式場なら、親族・友達・職場関係などをまんべんなく招待することが可能。
また、80人以上の大規模になると、親族・友達・職場関係に加え、前職の人、近所の方など、お世話になっている人も呼べます。優先順位をつけながら誰を呼ぶかを選びましょう。
予算で決める

結婚式では、招待客が1人増えるごとに料金は大きく異なります。そのため、あらかじめ予算を決めたうえで誰を呼ぶかを決めるのもおすすめです。
大まかな人数だけを出して、「自己負担額+(招待客の人数×ご祝儀3万円)」で計算します。
招待客1人あたりの予算は、式場にもよりますが、料理・飲み物・引き出物・引き菓子・招待状・席次表などを合わせて約6~7万円といわれています。
そのため、予算は50人規模の結婚式の場合約300万円前後、80人規模の場合だと約480万円前後が必要です。
予算を抑えて多くの招待客を呼びたい場合は、Web招待状を活用したり、席次表を手作りしたり、ムービーを自作したりと工夫すると予算を抑えられます。
パートナーの招待客とのバランスを考えて決める

結婚式の招待客は、自分だけが誰を呼ぶかを考えればよいワケではありません。パートナーと、招待する招待客層や人数のバランスが取れていることが必要です。
たとえば、片方が友人ばかりを呼ぶ、片方は職場関係ばかりを呼ぶといった具合に客層に大きなズレがあると、盛り上がれず楽しめない招待客が出てくるかもしれません。
そのため、「誰をどのぐらいの割合で呼ぶか」という点も2人で話し合い、バランスを取るのがベターです。
また、双方の招待客の人数差については、バランスが取れていないといけないという決まりはありません。よく話し合い、2人が納得する人数差に抑えておきましょう。
結婚式に呼ばれたら呼ぶべき

結婚式を挙げる場合、親族のみの結婚式を除き、「結婚式に呼ばれた人は呼ぶ」のが一般的。しかし、相手が遠方に引っ越していたり、出産直後であったりと事情がある場合は注意が必要です。
場所やタイミングなどによって、招待されても参加が難しい場合もあります。呼ぶかどうか決める前に、相手に相談してから決めるのがよいでしょう。
結婚式に呼ぶ招待客を決める流れ
①どんな規模・雰囲気で式を行いたいかをイメージする

まずは、どんな規模感、雰囲気で結婚式を挙げたいかをイメージしましょう。
・親族・友人メインの少人数を招待してアットホームな雰囲気で行いたい
・できるだけ大人数を呼んで豪勢かつ賑やかな雰囲気で行いたい
・親戚や職場関係などお世話になっている方々を招いて厳粛に行いたい
などをイメージします。すると、誰を呼ぶのかがおのずと見えてくるでしょう。叶えたい結婚式に合わせて、ゲストをリストアップしていくのがおすすめです。
②規模や予算に合わせて招待したいゲストの優先順位をつける

次に、結婚式の規模や予算に合わせて誰を呼ぶかの優先順位をつけてリストアップしていきます。主賓・親族などの絶対に呼ぶ方、上司や恩師、親友など呼ばなければいけない方などを優先して選んでいきましょう。
招待するか悩む場合は、呼ぶのがおすすめ。出欠を決めるのはゲストであり、結婚式に呼ばれなくてがっかりすることはあっても、招待されてがっかりする方はいません。
③招待客層や人数に合わせて式場を決定する

式のイメージやゲストの大まかな人数、立地なども考慮して式場を決めます。式場によって収容人数は決まっていますが、披露宴などでゲストの関係性を考慮して卓を決めると、全員が収まらない場合もある点も考慮しておきましょう。
ゲストを決めていくうえで、テーブルの配席、招待客人数のバランスはどうするかなども配慮しながら決めると後で困りません。
結婚式に呼ぶときに配慮が必要なゲストとは?

結婚式に招待することを決めたものの、招待するにあたって配慮が必要な場合もあるので注意しましょう。
個別・特別対応が必要な場合は、式場にお願いしたり、あらかじめ確認したりしておく必要があります。全員に気を配り、招待客に気持ちよく参加してもらえるように覚えておきましょう。
・遠方の招待客…宿泊ができるか否か、大きい荷物をクロークに預けられるか、着替えできる場所はあるか確認、空港や駅などからアクセスがよい式場を選ぶなど配慮をする
・妊娠中の招待客…料理やドリンクの個別対応ができるかどうか、クッション・ひざ掛けなどの有無などを確認
・小さい子供がいる招待客…おむつ替えスペース・託児所の有無を確認、子供用メニューの用意など
・1人で参加する招待客…事前に1人であることを報告、1人で参加するゲスト同士で顔合わせをする機会を設ける、同卓にするなど
・異性の招待客…親族に事前に関係性を知らせておく、親族が気にする場合は招待を控えるなど
結婚式に呼ばない人にも結婚報告をするなど配慮をする

結婚式に誰を呼ぶかを決めた後、結婚式に呼ばない招待客に対しても、結婚報告を怠らないようにしましょう。特に職場関係や友人への報告には配慮が必要です。
「入籍しました」という報告のみ、もしくは「式は身内だけで挙げることにしました」などと呼ばない理由を添えると丁寧です。
また、結婚報告のタイミングにも注意。結婚報告をする前にほかの友人から別の友人へ伝わってしまったり、SNSで先に報告してしまったりすると、「なぜ私には報告がないのか」「直接報告を受けていない」などと気分を害してしまう方もいます。結婚報告のタイミングは合わせて行いましょう。
詳しい結婚報告のマナーやタイミングについては、以下の記事を参考にしてみてください。
結婚式に誰を呼ぶかは式のイメージや規模から決めよう
結婚式に誰を呼ぶかは式のイメージや規模から、親族、絶対に呼ぶべき人、呼びたい人といった具合に優先順位をつけて決めていくのがおすすめ。
また、招待客を決めた後も、配慮が必要なゲストの対応をしたり、呼ばないゲストにも結婚報告をしたりと各方面への気配りが必要です。「結婚」というせっかくのおめでたいイベント。配慮を欠かさず、皆に気持ちよくお祝いしてもらえるようにしましょう。